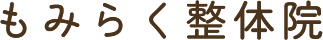★サイドプランク★
足から頭までを一直線に保持するプランク。
サイドプランクとはそれを横向きで行うストレッチ
方法です。
腹斜筋を鍛え、姿勢の改善、インナーマッスルなど
様々な筋肉の強化に繋がります。
①体をまっすぐにして横向きに寝る。
②頭を持ち上げ下側の肘で体を支える。
③両足を伸ばして重ねる。
④腰を持ち上げ頭・肩・膝・かかとまでを一直線にする。
⑤上側の手を腰にあててそのまま20秒キープ。
⑥反対側も同様に行う。
サイドプランクとはそれを横向きで行うストレッチ
方法です。
腹斜筋を鍛え、姿勢の改善、インナーマッスルなど
様々な筋肉の強化に繋がります。
①体をまっすぐにして横向きに寝る。
②頭を持ち上げ下側の肘で体を支える。
③両足を伸ばして重ねる。
④腰を持ち上げ頭・肩・膝・かかとまでを一直線にする。
⑤上側の手を腰にあててそのまま20秒キープ。
⑥反対側も同様に行う。